|
降誕節第11主日礼拝説教「神の無限に触れ」 日本基督教団藤沢教会 2011年3月6日
8 わたしの僕イスラエルよ。
わたしの選んだヤコブよ。
わたしの愛する友アブラハムの末よ。
9 わたしはあなたを固くとらえ
地の果て、その隅々から呼び出して言った。
あなたはわたしの僕
わたしはあなたを選び、決して見捨てない。
10 恐れることはない、わたしはあなたと共にいる神。
たじろぐな、わたしはあなたの神。
勢いを与えてあなたを助け
わたしの救いの右の手であなたを支える。
11 見よ、あなたに対して怒りを燃やす者は皆
恥を受け、辱められ
争う者は滅ぼされ、無に等しくなる。
12争いを仕掛ける者は捜しても見いだせず
戦いを挑む者は無に帰し、むなしくなる。
13 わたしは主、あなたの神。あなたの右の手を固く取って言う
恐れるな、わたしはあなたを助ける、と。
14あなたを贖う方、イスラエルの聖なる神
主は言われる。
恐れるな、虫けらのようなヤコブよ
イスラエルの人々よ、わたしはあなたを助ける。
15 見よ、わたしはあなたを打穀機とする
新しく、鋭く、多くの刃をつけた打穀機と。
あなたは山々を踏み砕き、丘をもみ殻とする。
16あなたがそれをあおると、風が巻き上げ
嵐がそれを散らす。
あなたは主によって喜び躍り
イスラエルの聖なる神によって誇る。
(イザヤ書41章8~16節)
五千人に食べ物を与える
10使徒たちは帰って来て、自分たちの行ったことをみなイエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。11群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々をいやしておられた。12日が傾きかけたので、十二人はそばに来てイエスに言った。「群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行って宿をとり、食べ物を見つけるでしょう。わたしたちはこんな人里離れた所にいるのです。」13しかし、イエスは言われた。「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい。」彼らは言った。「わたしたちにはパン五つと魚二匹しかありません、このすべての人々のために、わたしたちが食べ物を買いに行かないかぎり。」14というのは、男が五千人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、「人々を五十人ぐらいずつ組にして座らせなさい」と言われた。15弟子たちは、そのようにして皆を座らせた。16すると、イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。17 すべての人が食べて満腹した。そして、残ったパンの屑を集めると、十二籠もあった。
(ルカによる福音書 9章10~17節)
教会暦は、今週半ばに<灰の水曜日>を迎えます。この日から、キリストの十字架への道行きをおぼえる受難節の歩みが始まります。イエス・キリストの十字架の苦難と死の出来事を、私たちはいつから知らされたのでしょうか。おそらく多くの方は、教会に来てすぐであると思います。教会は、毎週礼拝の中で世々の教会に受け継がれてきた「使徒信条」を唱えます。「使徒信条」の起源には、主イエスの12使徒の一人ひとりが各々信ずるところを一言ずつ告白して完成されたという興味深い伝説があります。すなわち、「ペトロが『私は全能の父なる、天地の造り主なる神を信ず』と言った。アンデレは『父の御子であり、唯一の主なるイエス・キリストを信ず』と言った。ヤコブは『主は聖霊によって身ごもり、処女マリアより生まれた』と言った。ヨハネは『ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架にかけられ、葬られた』と言った。トマスは『よみにくだり、三日目に死からよみがえり』と言った。・・・」主の復活に及んで、「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ・・・わたしは決して信じない」と頑なに言い張ったトマスが、復活の主に出会って思わず「わたしの主よ、わたしの神よ」と言ったという出来事が伝えられていますが(ヨハ20:24~29)、そのトマスが、「使徒信条」において率先して主の復活を告白したと言います。もちろんこれは伝説ですが、12使徒に宛がわれるほど簡潔にまとめられた「使徒信条」は、三位一体の神を告白しています。中心に置かれるキリストに関する告白はしかし、弟子たちが共に過ごしたキリストの公生涯についてほとんど述べられていません。その誕生から直ちに十字架へと進むのですが、主イエスがどのようにこの地上を歩まれたのかということは私たちの最大の関心事です。しかしながら、主イエスの地上での宣教が、すぐさま教会を造り上げたのではありません。その出発点は、主イエスの十字架と復活の出来事にあります。十字架で躓いた弟子たちが、主の復活によって新しく奮い起こされ、主を信じる人々の群れが生まれて、教会が始められていきます。裏切りと悔い改めを経験したからこそ、弟子たちは主を真に語り始めることができました。そう、あのとき主はこのように言われたじゃないか、このようにされたではないかと、主イエスと歩んだ日々が生き生きと想起され、弟子たちにも、そのときにはわからなかった主の御言葉の意味に目が開かれて、本当に分かるようになったのです。
本日の福音書の物語<5千人の供食>は、4つの福音書に共通して伝えられる唯一の奇跡物語です。この章の後半では、主はエルサレムに顔を向け、十字架に向かわれる決意をされます(9:51)。主を追ってつめかけて来る人々を主は迎え、神の国について語られ、また病の人にはいやしを行われました。傍で日が傾いてきたことを気にかける弟子たちは「群集を解散させてください」と主に申し出ます。弟子として賢明な判断ではなかったかと思います。先を見越して、今解散してくださらなければ大変なことになるだろうと、弟子たちは責任を感じています。目の前にいる人々、癒しの順番を待っている人々は、疲れています。病に弱りながらもやっとのことで主について来たのかもしれません。一度解散して、出直す力が残されていたでしょうか。近くの里や村に行く力さえ無い人もあったかもしれません。病を持つ人の生活は楽ではないはずです。病気のために働くことがままならない人、多くの医者にかかり全財産を使い果たしてしまった人、主に近づく人たちの病は、複合的な生活苦の元凶でもありました。確かに、中には裕福な人もあったかもしれません。主イエスの噂を聞いて、一目見たい、教えを聞きたいと思っていた人たちの中には、何不自由なく暮らすような健康な人もあったでしょうし、直接的な動機ではなく付き添いで来た人、興味本位でやって来た者もあったでしょう。とにかく、夥しい人たちに囲まれて、弟子たちは搾り出す知恵もないのです。
「わたしたちにはパン5つと魚2匹しかありません」正直に申告している通りです。「~しかありません」「~以上のものはありません」という否定的な言い方が、ブレーキをかけています。「このすべての人々のために、わたしたちが食べ物を買いに行かないかぎり・・・」(それは絶対ムリです!)弟子たちの気持ちが伝わってきます。「というのは、男が五千人ほどいたからである」。ムリなものは、ムリです!ルカもまた、数字の現実を伝えています。人数を把握するだけでも、気が遠くなってしまうような夥しい人たちが、目の前に集まっていました。5千人以上の人々に対して、パン5つ、魚は2匹。約1000人に1個・・・? 計算しても仕方ないような、いくらポジティヴに考えても足りるはずがない、手の施しようのないような状況なのです。こんなにいるのに、それに対してたったこれだけ? こんなもの何の役に立つかと思うほどです。与えたい気持ちは山々でも、あまりに粗末で、自分たちの食べる分さえままならないほどです。いったい私たちに何が提供できるというのでしょうか。しかし弟子たちの良いところと言えば、主に従うところではないでしょうか。ムリです!という正直な気持ちを見せながらも、「人々を50人くらいずつ組にして座らせない」との主のお言葉に、弟子たちはすぐさま心を開いています。主のお言葉のとおり、「そのようにして皆を座らせた」と言います。私たちはこの弟子たちのようにできるでしょうか。主は、まったく「~しかありません」という訴えを意に介せずに、弟子たちに指示されます。弟子たちが今まさに持っているもの、手にしているところから始められます。病の者も健康な者も、貧しい者も富んでいる者も、年配の者も年若い者も子どもも、主のもとにやって来たすべての者を空腹のまま帰さずに、大きなグループにして留まらせます。主はすべての者にその食事が必要であると思われたのです。ユダヤの食事の慣習に従って、主イエスは食卓を始められます。「イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた」とあります(16節)。パンを「取り」(ランバノー)、「讃美の祈りを唱え」(エウロゲオー)、「裂いて」(カタクラオー)、「与える」(ディドーミ)、これら4つの主の所作(動詞)はまた、「主の晩餐」を思わせる言葉です。これらの言葉は、「5千人の供食」が「主の晩餐」の前触れであることを伝えています。原始教会において「パン裂き」という言葉は「聖餐」という特別な礼典を意味しました。「裂く」(カタクラオー)とは、非常に印象的な動作です。同時に「裂く」とは、大変暴力的な言葉です。主イエスは最後の晩餐で、この「裂く」という動作を、御自らの肉体になぞらえて語られました。「これはあなたがたのために与えられるわたしの体である」(ルカ22:19)。あなたがたに与えられるために私は裂かれる。主イエスの存在そのもの(血、肉)が、私たちの食べ物となると言われるのです。
その言葉を弟子たちは、思い出して深く知りました。「主の晩餐」のその席ではわからなかったことが、主の十字架と復活の出来事を通して、今は、わかるのです。私たちはまた、弟子たちとともに主のご生涯の歩みをたどる巡礼を歩んでいます。5千人という人々を豊かに養われた主の物語。確かにあのときに弟子たちの手元にあったのは、5つのパンと2匹の魚でした。「魚」(イクテュース)は、焼くなどしてパンと一緒に食べる副食物であるそうです。パンと共に食卓の主が手に取られた「魚」がどう増えたのか、残ってかごに集められたなどということは記されていませんが、「魚」もまた食卓を豊かにしたでしょう。教会の初めの時代、迫害の下にあったクリスチャンの間で、「魚」(ICQUS*1)は象徴的な意味を持ちました。「イエス・キリストは、神の子、救い主」(Ihsouj Cristoj Qeou Uioj Soter*2)の頭文字が、「魚」(ICQUS)であるからです。私たちの教会のステンドグラスにも「魚」(ICQUS)の告白が掲げられています。「5つのパンと2匹の魚」ならぬ、「命のパンと信仰告白の魚」が今、私たちの礼拝堂に備えられています。「命のパン」はそれによって生きる神の言葉です。私たちは、聞くことにより、味わい見ることにより神との深い交わりの中に生きる者とされるのです。
本日私たちの礼拝には聖餐が備えられています。この食卓の交わりは、すでに天に召された雲のような証人たちとの交わりでもあります。私たちにさまざまな「過去」を想起させ、私たちに「現在」生きて共にあられる主を知らしめ、さらに私たちの「未来」の祝福を指し示す信仰の長い旅路の道標です。「イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠に変わることのない方です」(ヘブ13:8)。
キリストを通して、私たちは神の永遠に触れています。私たちは限りある人生の中に生きており、それは質素で、取るに足りない、短いものかもしれません。私たち自身は、あまり魅力的とは言えない者かもしれません。この一生のうちに何が為しえるだろうかと、誰もが問うています。そして何も為しえないことに愕然とします。しかし、私たちはこの葛藤の中で、人生の意味に疑問を感じずにおれなくなった中で、限りある存在であるこの私が、今、神の無限に触れている事実に出会うのです。これは途方もない現実です。主は、私たちを究めて、私たちのありのままを受け入れて、ご自分を差し出してくださっています。「取って食べなさい」と。私たちが、ありのままの自分を受け入れるということは、自分の限界を認めることでもあります。自分は、本当はもっと良い存在なのだ、もっとできるはずだ、と言い張れば言い張るほど、そうではない自分自身のギャップに苦しみます。自分の思い通りにならずに、私はこれだけの者なのかと思わせられるような惨めな経験を余儀なくされます。自分の不足や不得手な部分が見えると、億劫になるのです。持っていないことや失敗して傷つくことが怖いと無意識に自己防衛します。しかし、何もかも持っている人はいないですし、むしろ誰もが必要とするものを私たちは最初から持っていません。私たちは最愛の人に対してさえ、メシア(救い主)にはなれないのです。またすべてのことを一人でするように、と主は言われません。私たちには、それぞれに与えられた分があります。主は今日、「あなたがたが・・・与えなさい」と言われます。「あなたたち」とは、私たちです。主は全能でいらっしゃるのに、「あなたたちが」と言われます。
私はこの3年間を過ごす間、礼拝の聖餐の時間はオルガンの陰に座っていました。私のためのパンと杯を待っていました。配餐の奉仕をしてくださる役員の方がそばに持ってきてくださるのを待っていました。それなのに主は、今度は「あなたが行いなさい」と言われます。昨晩、村上先生と二人で聖餐の練習をしたときに「傍にはいるけれど、あなたがするのだからね」と言われて、私がするのか・・・後戻りできないのだな、という気持ちになりました。しかし確かに「わたしが」行うのですが、この食卓は私と皆さん、「わたしたちが」行うものです。一人でするのではありません。主がしてくださることを、私たちは主の弟子として行うのです。
「≪信徒は≫パンと魚を待つ、≪弟子は≫漁師になる」と、ある人は言いました。「≪信徒は≫天の国に入ることを目標とする、≪弟子は≫他人が天の国に入ることを目標とする」と。私たちはただ救われることではなく、救われた者として共に生きることに招かれています。主は、私たちを満たす奇跡ではなく、私たちが満たされ、満ち満ちて留めておくことができない、溢れ出すような奇跡を行われます。この恵みは、もはや私たちがどんなに数多くても、たくさん欲している飢えた者であっても、そこに収まりきれない祝福なのです。尽きることのない主の祝福を希望としているからこそ、どんな困窮に遭っても、私たちは主の弟子として差し出すことができるのです。私たちは、命のパンを味わいましょう。私たちに与えられた大切な一人にもたらす者として歩み出しましょう!
| *本文中の (ICQUS) と (Ihsouj Cristoj Qeou Uioj Soter) の文字は以下: |
*1「魚」
(ICQUS) |
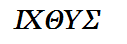 |
*2「イエス・キリストは、神の子、救い主」
(Ihsouj Cristoj Qeou Uioj Soter) |
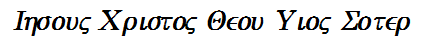 |
|